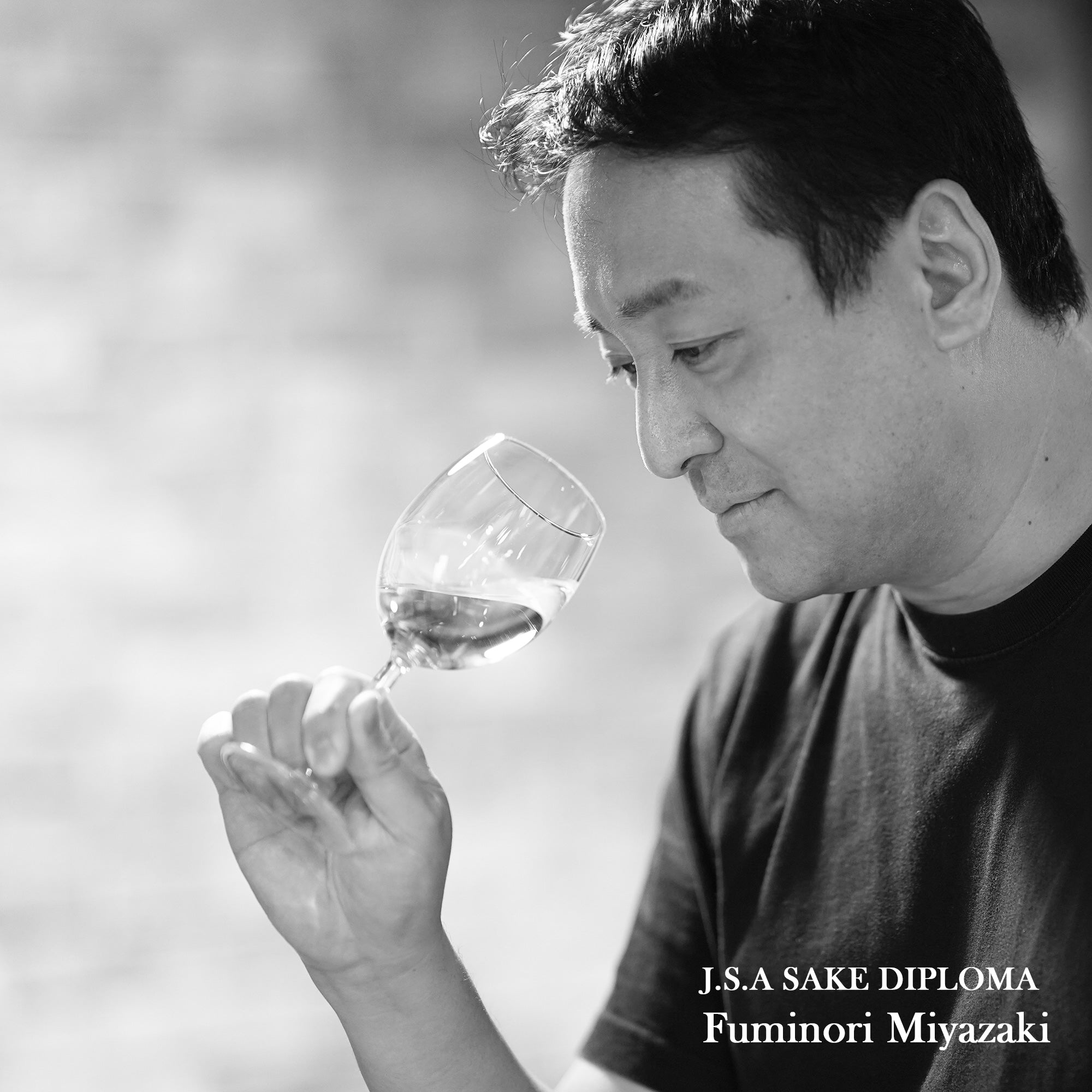多くの日本酒は、秋に収穫されたお米で、冬から春先にかけて仕込まれたものですが、年間を通して酒造りを行う「四季醸造(しきじょうぞう)」という酒造りがあります。

四季醸造の説明の前に、なぜ日本酒は冬を中心に造られるのか?というと、秋にお米が獲れ、そのあとの季節である冬に酒造りが始まるというのもありますが、何よりは外気温の要素が一番の理由です。
暖かいと雑菌が繁殖したり、醸造中の醪(もろみ)は熱を発し、温度管理の都合で寒い季節の方が、温度をコントロールしやすいという点に優れます。
また、人材確保という観点からも冬の酒造りではメリットがあり、農閑期だと出稼ぎなどの労働力を確保しやすかった点が挙げられます。

さて、四季醸造についてですが、文字通り「春夏秋冬」酒造りを行うことであり、これは近年大手の蔵元で行われることが多くなってきました。
四季醸造を可能にしたのは、空調設備です。外気温に影響されない低温の温度管理が出来れば、冬の寒い時期と同じような酒造り、酒米の管理が可能です。
ちなみに、四季醸造はもともと各季節ごとに合わせた酒造りのことを言っていた時代もあるようですが、今は空調設備の整った蔵元で年中酒造りが行われることを指します。

四季醸造で近年有名なのは山口県岩国市にある旭酒造さんの「獺祭(だっさい)」で、常に新酒が市場に出回るようなイメージですが、逆を言うと春夏秋冬のそれぞれの時期に限定で発売される「旬」の味わいを感じにくいという点があるかもしれません。
どちらが良いかという話ではなく、そういった日本酒の製造方法において変化があるのが、近年の酒造りです。

年間を通して製造を行う四季醸造のメリットをまとめますと
1.小仕込みである
大きなタンクを使用して一度にたくさん造るのではなく、小さなタンクを数多く用意し(獺祭の蔵元では200個~のタンクがあるそうです)、毎日分析をかけながら酒造りが行われています。
市場の需要に合わせて酒造りの量を変えたり、新商品の投入も早くできる可能性があります。
2.年間を通して酒造りを行うので、蔵人のスキルアップが早い
冬場にしか酒造りを行わない蔵と比べ、毎日酒造りが行われるので、普通の蔵元が1年間に仕込む回数を数ヶ月でその回数を行えるそうです。
つまり四季醸造の場合、年間の酒造りの回数が普通の酒造りよりもはるかに多くなるので、蔵人のスキルアップが早く、品質も通年で高品位レベルを保つ事ができるそうです。
2016年秋に実際に旭酒造さんを見学させて頂きましたが、これからの時代は四季醸造のメリットが活きてくる時代になるような予感がしております。